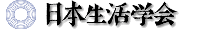周縁化されやすいコミュニケーションへの着目から
庄子諒氏(東洋学園大学 人間科学部 専任講師)
聞き手:土居浩(ものつくり大学)・清水健太(早稲田大学)
*所属などはインタビュー時のものです
まずはこれまでの研究歴、研究をはじめたきっかけや取り組んできたことを、聞かせてください。
専門は社会学です。地元は福島県福島市で、2010年4月に立教大学の社会学部に入学、それを機に上京しました。
入学した当時は、そもそも研究については考えていませんでした。ただ入学した年の年度末である2011年3月、学部の1年生から2年生になるタイミングで、東日本大震災が起こりました。その出来事が一つきっかけになって、地元や震災を自分なりにどう考えていくか、地元とどう向き合っていくか、それが問題意識として湧き出てきました。その後、学部3年生に上がるタイミングで、ゼミに入りました。そのゼミには、各自でテーマを持ち調査をして論文を書く課題があったので、地元・福島のことをテーマにしようと思いました。時期的にちょうど2013年末、震災後初の国政選挙(衆議院議員選挙)があり、震災後の福島の選挙がどんな様子になるのか知りたいと考え、選挙期間中に地元へ戻りフィールドワークをしました。それが、一番最初の調査研究、手探りでしたけれど最初のフィールドワークです。
入学した時点では、卒業後も続けて研究するとは考えていなかったとのことですが、そもそも「社会学部」を選んだ理由あるいは心当たりはありますか?
記憶がおぼろげですけれど(笑)、私は元々ラジオが好きで、高校生の時からよく深夜ラジオを聞いていました。なので当初は、メディアの勉強をして、卒業したらメディアのつくり手になりたいと考えていました。立教大学社会学部にはメディア関連の学科があり、私自身は社会学科でしたが、メディアに関連する科目がたくさんあると入学前に情報を得ていたので、進学しました。
深夜ラジオというとFMではなくAMリスナーですね。どんな番組を聞いていましたか?
私が高校生のとき、地元の福島にはAMラジオ局がひとつしかありませんでした。そこでは「オールナイトニッポン」しか放送してなかったのですが、当時ちょうどお笑いコンビ・くりぃむしちゅーのオールナイトニッポンがすごく人気があった時期で、友人に勧められて聴き始めました。とはいえあくまで聴く専門で、私自身は「ハガキ職人」にはならなかったです(笑)。
日本生活学会の博士論文賞を受賞された庄子さんの「笑いへの離脱/笑いへの拘束:原発事故後の福島における震災経験とユーモアの生成過程にかんするコミュニケーション社会学的研究」は、人はみんな体験しているはずなのに見ていない領域、取り上げられない領域に注目されている印象を受けていました。その領域の声を拾い上げる姿勢は、深夜ラジオのリスナーであったことと、深層で繋がっているように思いました(笑)。世間の流行・大きな潮流に乗る姿勢ではなく、クラスの一人か二人くらいは反応する話題にこそ注目する姿勢のことです。ですが、今おうかがいした最初のフィールドワークは震災後初の選挙だったとのことで、むしろ大きな潮流に乗る調査だったとお見受けしました。
初発の問題意識として、やはり震災のことがあります。私自身は東京に憧れ、当時はこんな地元を早く出ていこうと思って、上京しました。けれどもその地元が、震災があり「被災地」と呼ばれるようになり、誰も知らなかった地名を全国の人が知るようになり、ニュースで毎日のように報道され、地元の人が「被災者」と呼ばれて色々な語りをしている……これらの状況が、とにかくすごく衝撃的で、浜通りや中通りも関係なくひとくくりに「福島」や「被災地」と呼ばれるイメージの流布に、違和感を覚えました。
そんなわけで最初の調査では、「福島」や「被災地」等々と一枚岩的には呼べない、多様な立場の人たちがいることを描き出せたらいいと思い、フィールドワークしました。震災からまだ2年ほどでしたので、そんな問題意識を持っていましたね。
その調査の成果や手応えはいかがでしたか?
実際に調べてみると、その当時、福島市とは別の土地から避難している方々が多くいました。自分が高校まで暮らしていた地元の福島市に、自分の知らない色々な方々が暮らしていることを発見できたことは、大きかったです。調査で地元に帰ると、まずは震災前と変わらない風景が目に入るのですが、とはいえ目に見えない部分も含めて変わった部分がたくさんあることを知る調査になりました。
その次の調査研究は、卒業研究になるのでしょうか。
そうですね。学部4年生で卒業論文に取り組むとき、私は福島のことを継続的に調査しようと思いました。そのとき、自分のもう一つの問題意識として、私と同世代の福島の若者たちが、震災のことをどう受け止め、この先どういう進路や生き方をしようとしているのか、に関心がありました。例えば、地元に戻って「地元のために」「被災地のために」と考える人もいれば、そうでない人もいるだろう。ですので元々の地元の同級生や先輩・後輩などつてをたどり、一人ひとりにインタビューする調査を企画し、福島に関わりのある数名の知人にインタビューをし、福島の震災の問題とどう向き合っているのか、どう感じているかをテーマに卒業論文を書きました。
卒業論文に対する手応えはいかがでしたか?
地元の同世代の若者たちの中には、一度上京したけれど地元に戻り就職して働こうと選択した人もいれば、東京に残って働き東京から被災地のために何かできないか探ろうとしている人もいました。いろんな選択、考え方をしている同世代の若者がいることを知ることができたのは、自分自身としてはとても意味のあることでした。同時に、新たな問いとして浮かんできたのは、その後の研究にもつながる当事者性の問題です。震災や福島のことに向き合うとき、どんな立場からその問題に向き合うのか、自分の経験をどう考えるのか、各自のポジショナリティが大きな問題になっているし、そこにまだまだ問いが残っている印象を受けました。ですので、インタビューをしてまとめてはみたけれど、十分に研究しきれたとは感じられなかったところもありましたね。
「問いが残っている」と話されましたが、その後その問いは持ち続けることになるのでしょうか。
どう地元のこと、福島のことに向き合うのか、距離感や立ち位置が、自分の中で問いとして残ったように思います。インタビューした相手は福島で震災を経験して、その後の大変な時期も福島で過ごしていました。それに対して、私自身は震災当時すでに東京で暮らしており、震災も東京で経験し、東京でマスメディアやSNSなどメディア越しに福島に関する情報を受け取っていました。まさに私自身の立ち位置の問題で、まだまだ色々考えることがあるのではないかと思い、それが大学院修士課程に進学するきっかけにもなりました。ですので修士課程に進学し、学部から引き続き奥村隆先生にご指導いただきました。
修士に進学しての研究を紹介してください。
その時期、だんだん地元で、震災や原発事故の話題をあまり語らなくなってきたという実感がありました。震災直後はあれほど、原発事故に関する問題が毎日報道され、情報も流れ、毎日のように語られていました。しかしだんだん語る場が少なくなり、さらには語られにくくなっていった実感がありました。そんな雰囲気の中で、どんな震災経験の語り方がありうるのかだろうか?ということを考えるようになりました。自身の震災経験をどう語るか、という部分への着目ですね。
ただ修論での具体的なテーマ設定には、すごく悩みました(笑)。演習科目で津波の被災地に行った取り組みなどはすごく学びも多かったのですが、自分自身のテーマはなかなか決まりませんでした。地元の福島市をフィールドにすることだけは決めていましたが、ではテーマは?着眼点は?事例は?が定まらなくて。東京から福島への移動は時間もほぼ気にならないので、夏休みに長めに帰省して調査するだけでなく、短期的に数日間だけ戻って調査するなど頻繁に行き来はしていて、例えば、地元で新しく始まったお祭りやイベントに注目しようとか、あるいは震災後に新しく生まれた市民の語りの場をつくるような取り組みに注目しようとか、探り探りながら参与観察やインタビューに着手してはいたのです。
「これだ!」とテーマが決まったのは修士課程のいつ頃でしたか?
2年生の前期の終わり、夏休み直前ぐらいだったかと(苦笑)。とにかく2年生の夏、指導教員とも相談して「これにしよう」と絞り込んだテーマが「ユーモア」でした。ギリギリのタイミングでしたから、修士論文としては荒削りというか、アイディアはともかく調査が十分とはいえなかったのですが、このテーマを見つけられたのは修士論文の一つの成果だと思っています。
震災後の福島においてどういうコミュニケーションの形があるのかを考えた時、震災は深刻な問題ですし、真面目に、堅く語られやすいテーマなのは間違いないです。しかし地元で過ごす中で、そういう堅いコミュニケーションばかりではないと気がつきました。震災直後でも、日常的なコミュニケーションというものはありましたし、その中にはユーモアや笑いが生まれる局面もあったと、振り返って考えるようになりました。それをテーマにできないかと考えたのが最初のきっかけだったと思います。
公開されてます庄子さんの修論要旨「笑う福島/笑わない福島:原発事故後のユーモアに関するコミュニケーション社会学的研究」によれば、福島のAMラジオ局で働く社員・アナウンサーへのインタビュー調査も含んでいます。冒頭でうかがった、進学時の関心と緩やかに繋がりますね。
そうですね(笑)。地元にいるとき、AMラジオ局の人と知り合いになりました。その時はそれ限りでしたが、修論のテーマを決めて、地元でフィールドワークするときに、ラジオなどメディアも取り上げたいと思いました。そのラジオ福島は、震災後も放送を休みなく続けていたことでも話題でした。ですので、その点も含めてインタビューしたいと思いラジオ局を訪ね、テーマのことや「笑い」という切り口を話題にしたら、開口一番「そんなことはできないよ」との反応で、その通りだなとも思いました。「笑い」や「ユーモア」といったコミュニケーションは、「できる」だけでなく「できない」ことも含めて重要だと気づいたことが、修論の調査でしたね。
なるほど、修論タイトルにある「笑う/笑わない」の「/(スラッシュ)」は、「できない」ことも含めて重要だとの気づきが反映されているのですね。庄子さんの生活学会での発表タイトルには「/(スラッシュ)」を使われることが多い印象があったのですが、その初発の問いは修論だったのですね。修論に対する周囲の反応は、いかがでしたか?
修士課程の段階では対外的に発表していないので、学内のゼミや修論発表会などでの反応になるのですが。自分自身でも、このような切り口で震災や福島のことを調査するのは、さすがに変わっているテーマだと思っていましたので、どういう反応になるのか当時から気にしていました。ひとまず興味深いテーマだと受け止めてくださっていたように思いますし、それがすごく励みになった記憶があります。
庄子さんの博士課程への進学は、2017年でしたね。俗に「文系の博士課程には先がない」などと言い伝えられていますが(笑)、進学するのに逡巡はありませんでしたか?
あまり思い出せませんが(笑)、修論に取り組む中で、テーマは見つけたけれど十分できなかった、もっと研究を続けたいという思いもありました。また修士課程のときに、博士課程の先輩とも触れ合い、こういう進路や取り組み方もあると知れたのは大きかったですね。周囲に進学を止められたりした記憶はなく(笑)、自分で選んで進学した気がします。とはいえ、もちろん当時から将来への不安はずっとあったと思いますが。
時期としては少し前後するとは思うのですが、橋本裕之『震災と芸能 : 地域再生の原動力』の書評や、その橋本さんも加わっての季刊民族学での座談会が公表されていますよね。これまでうかがった研究の流れとは、やや異なる文脈かと思われますが……
これは立教大学の修士課程で、橋本先生が担当された科目がきっかけです。『震災と芸能』がテキストで、そのレポートを提出したら、橋本先生が「これ、書評として活字にしたらどうか」と仰ってくださったのです。座談会も、その延長上ですね。
この書評をあらためて読みますと、大半が当事者性の話題で占められていますので、その点ではこれまでうかがった研究の流れにしっかり棹さしておられますね。そして立教大学で学ばれた後、博士課程では一橋大学に進学されました。
ちょうど、指導教員の奥村先生が、大学を移られるタイミングでもありました。博士課程に進学するとき、他の大学院も検討したらどうかとうながされ、一橋大学の社会学研究科を選びました。一橋での指導教員は、小林多寿子先生です。小林先生は社会学の中でも質的調査がご専門なので、調査について本格的に学べることは、修士までと大きく異なる研究環境でした。周囲にも色々なテーマで研究を進めている人が多くいる環境でした。
すでにご自身で質的調査に取り組まれてきて、博士課程から大学を移られたことで、それまでの調査の流儀というかお作法の違いなどは感じられましたか?
一橋大学の社会学研究科は、外部から進学してくる大学院生も多くいましたので、それほど違和感はありませんでした。ただ小林先生の主なテーマに「ライフストーリー」があり、その濃密な調査方法で難しい研究テーマに取り組む院生もいました。それと比べると、自分の調査やテーマとは「重み」が違うかもしれない、と感じたことは当時あったかもしれませんね(笑)。
最初の学会発表はどちらでしたか?
社会学の学会の中でも、震災や災害に関する研究が多い「環境社会学会」で修論発表の企画があり、そこで発表したのが最初でした。一橋大学では、外部の学会で積極的に研究発表している院生が多くいましたので、自分も色々な学会で発表しようと、社会学の一番大きな学会である「日本社会学会」や、理論研究にも関心があったので「日本社会学理論学会」で、発表を重ねました。
日本生活学会に関わるようになったのはどういうタイミングでしたか?
日本生活学会を知ったのは、小林先生の指導を受けるようになってからでした。先生が生活学会で活動されているのは知っていましたが、先生から直接に入会するよう言われたわけではありません(笑)。ただ大学院の科目で、小林先生の担当された社会調査の講義で、今和次郎の話が出たのです。それまで今和次郎のことをほとんど知らなかったのですが、先生が社会学以外の調査を取り上げ、銀座風俗調査などが取り上げられていました。こんな面白い、ちょっと変わったフィールドワークのやり方があるのか、とすごく印象に残っています。
あわせて、先にも挙げたいくつかの学会で研究発表を重ねる中で、私の研究テーマにしっくりくる学会となかなか巡りあわず、そもそも横断的テーマなので、とにかく色々な学会で発表したいと考えていました。そんな中、日本生活学会は自分の研究テーマにも深く関わるかもしれないと期待して、入会しました。
一橋大学へ移られてから、小林先生経由で、今和次郎の調査方法を学ばれたのですね。
はい。その考現学の方法で取り組もうと研究仲間に提案した成果が、研究論文賞をいただいた「野外飲酒とはいかなる飲み方なのか?:池袋西口公園における考現学的調査を通して」です。この研究チームは私を含め4人のほぼ同世代で、立教大学の大学院で知り合い、それぞれ通学で池袋に馴染みがありました。4人それぞれ専門分野は異なるけれど、共通して関心を持った池袋西口公園をフィールドに調査・研究できないかと、ずっと考えていたところに、私が考現学的方法を知り、仲間の賛同を得て、採用となりました。
あらためて一橋大学で調査方法を学ぶわけですね。それまではどのように学ばれたのですか?
立教大学での指導教員である奥村先生は、専門こそ理論系でしたが、そのゼミでは学生は調査するよう指導を受けました。学部の2年生まで社会調査が必修科目なので、基礎的なスキルはそこで一通り学んでいるからと、ゼミではインタビューやフィールドワークを独りで行い、独りで成果をまとめる取り組みをしていました。ただ実際のところ、先輩も後輩もそれぞれ手探りで調査を行っていたと思います(笑)。
一橋大学に進学してからは、より多様な方法があると知り、それぞれの調査方法を面白いと感じ、社会調査それ自体にも関心を持つようになりました。自分の調査はインタビューを中心に行ってきましたが、それとは別のプロジェクトやテーマで色々な調査方法を実践してみたいと思うようになり、実際に色々試してきました。
その「試して」みた一つが、森岡清美による調査を再検討した論文「調査される側にとって森岡清美の調査経験がもたらしたもの:1950年代の浄土真宗寺院調査にかんするリスタディから」になるのでしょうか。
これはもともと小林先生が関わっておられたプロジェクトの一環で、私は後から参加した形です。森岡先生のご自宅に調査資料が全部保管されており、その整理をしながら、これまでの森岡清美の研究を学び直すプロジェクトを進める中で、私も一つテーマを見出して調査・執筆しました。森岡先生は自伝も残されていて、ご当人にも何度かお会いしインタビューをする機会にも恵まれ、その中で私が着目したのは、1950年代のフィールドノートです。ノートだけでなく、当時の写真も丁寧に保管されてあって、とても丹念な調査をされたことが、時代を経てもよくわかる調査資料でした。後々大家と呼ばれることになる森岡先生が、社会調査の方法も現在ほど体系立てられていたわけではない1950年代に、ましてや便利な移動手段などもない時代に、地道に調査をされていたことを知ったのが、とても印象的でした。
進学されて、あらためて調査方法論への関心も高まり、まさに「よし、これからだ!」のタイミングで、コロナ禍に遭遇されたかと思います。その当時のことを振り返ってもらえますか。
一橋大学に進学して2年目くらいから、小林先生の学部ゼミで、調査実習にTAとして同行するようになりました。フィールドは福島県南相馬市で、その3年目でコロナ禍になり、調査実習をどう進められるのかが大きな課題でした。先生や学生と色々議論をした結果、その年にも感染防止対策をした上で、調査実習に行きました。当時の調査テーマは相馬野馬追で、その関係者には高齢者も多かったものでしたから、感染防止対策には細心の注意を払いました。私たちが取り組んだ対策も含め、小林先生との共著論文「コロナ禍のフィールドワーク:福島県南相馬市における相馬野馬追調査に取り組む一橋大学社会学部小林ゼミナールの場合」にまとめています。
一方で、私自身は博士課程の4年目になったところでした。調査に出るのは相当難しい状況になり、これは、これまでの調査を基にして、自分の調べたこと、考えたことを集中してまとめる時機なのだろうと思いました。指導教員の定年が近づいていた事情もありますが、最終的に博士課程の5年目に論文をまとめ、修了しました。
博論をまとめるのとほぼ同時並行的に、池袋の野外飲酒についての共著論文をまとめられました。以前から共同研究されていたとのことですが、その投稿先として『生活学論叢』を選んだきっかけは何でしょう?
じつは共同研究の成果は、立教大学の紀要を主として「池袋西口公園調査研究ノート」や、カルチュラル・スタディーズ学会で発表する(カルチュラル・タイフーン2019)など、研究仲間それぞれを筆頭著者として公表してきました。最近も「池袋西口公園再整備による建築環境の変化とその企図:フィールドノートと政策関連資料から」として公刊しています。
そもそもの池袋への関心は、池袋西口公園の再開発、かつてのテレビドラマ『池袋ウエストゲートパーク』と同じ風景だった公園が、2019年に再整備されて新しい公園になる。そのプロセスを見届けようと、仲間とフィールドワークをしたり議論をまとめたりしてきました。新しい公園になってからも、何か調査をしようとなって、野外飲酒というテーマを見つけました。ちょうどコロナ禍で、感染対策上、野外で酒を飲むのは悪いことだと話題になっていた時でした。池袋西口公園には、昔から野外で酒を飲んでいる人がいましたが、そういう「悪い」飲み方だけじゃないことをフィールドワークで実証的に研究してみよう、それなら研究方法として考現学はどうだろうと研究仲間に提案し、面白そうだと賛同してくれて調査を始めることになりました。
考現学を研究方法として調査をまとめるのだから、日本生活学会に投稿することを最終的なゴールにしようと、研究方法とその発表場所を念頭に置いてフィールドワークを始めましたね。

【図4】夜19時すぎ、池袋西口公園のベンチに腰掛けて滞在する人びと。再整備によって設置されたモニターには、COVID-19感染拡大防止を呼びかけるメッセージが頻繁に映し出されていた。(2022年4月撮影)
あらためて庄子さん自身が追求されている研究テーマの「ユーモア」について、お話しください。ここまでのお話しでも、色々な試行錯誤があったことをうかがいましたが、自身のテーマとしてどのように練り上げてこられたのでしょうか。
「ユーモア」というテーマに着目しようと決めた後、それをどう研究として位置づけていくか、これまでも現在もなお悩んでいる部分ではあります。いわゆる災害研究では、社会学はもちろん、災害の被害や社会的影響に着目することが多いです。その語り方も、苦難や喪失に注目してきたように思います。これらがとても重要なテーマなのは間違いありませんが、同時に、そのような過酷な状況を人々がどうやって生き抜いてきたのかという視座もきわめて重要だと考えたとき、ともすればあまり重要とは思われない笑いやユーモアのようなコミュニケーションの形が、何かしら役割を果たすこともあるのではないか。そのように、社会学的な災害研究の中に自分のテーマを位置づけられるのではないかと考えたのですが、ここに至るには時間がかかりました。このテーマを社会学の学会などで、災害研究に取り組んでいる色々な方がおられる場で発表すると、場違いというか、伝わらない印象を受けることも、経験してきました。そういう経験の一つひとつがテーマを練り上げる土台になりました。
災害研究のある種「メインストリーム」で揉まれつつ、それにめげずに庄子さんがご自身のテーマに取り組んでこられたことの背景の一つには、先ほども出てきた「当事者性」と言いますか、出身地である福島のことに取り組むこともあるかと推測するのですが、その辺りはいかがでしょう。
この研究テーマに取り組み、あちこちで発表したり調査したりする中で、こういうテーマで福島や災害のことを研究している人はどうやら私だけのようだと把握したことなどは逆に励みとなりました。もちろんご指摘のように、私の地元を扱っている点も大きいと思います。とはいえ当事者性がクリアになったというよりは、より悩みが深まったと言いますか。研究者として福島を眼差しまとめる態度と、そこが私自身の地元であることの距離感について、かえって考えさせられています。ずっと考え、悩み続けていくプロセスの中に、私の研究活動があり、地元での時間があるという、そのような思いを強くしている気がします。
とはいえ自分の研究については、いわゆる「当事者研究」とも少し異なる距離感を、自分の中では感じています。自分がどのように福島や、福島が抱える問題と関わっていくのかについては、ずっと悩み続けているところです。そのこと自体を問いにしたり、ましてや成果にすることは、まだできていません。ですがそのこと自体を問いにしていくことも、生活学会と関わりながら、自分の中で進めていけるといいなと思っています。
最後に、今後の展望をお聞かせください。
共同で取り組んでいる池袋西口公園の調査は、今後も発展させつつ継続したいです。池袋全体の再開発がこれから始まります。15年から20年の単位で西口エリアが大きく変わる計画になっており、その間のプロセスも追いたいです。
また社会調査方法論への関心も継続していますので、生活学における考現学なども含め、学びつつ深めていきたいと考えています。
これまで震災下での笑いやユーモアを取り上げてきた個人研究においては、今後は、これらのいわゆる「遊び」のコミュニケーション、社会の中で大事にされない、副次的に扱われがちなコミュニケーションに着目する形で、さらに研究テーマを広げていきたいとも考えています。
本日はありがとうございました。
(インタビュー日:2025年7月2日)
インタビューを終えて(聞き手の一言)
【清水】
ご自身の故郷である福島市を調査フィールドに研究を行う中で、当事者性をめぐる問いがクリアになったというよりはむしろ深まり、考えさせられ続けている。この点がとりわけ印象的でした。私も庄子さんと世代が近く(2011年入学)、東日本大震災で被災した地域との関わりがその後の進路や研究に大きく影響を与えました。学びと同時に、共感するところも多いインタビューでした。
私も、庄子さんと世代的にほぼ同じというか、東日本大震災の都市に大学に入って、「ボランティア」や「まちづくり」を切り口に東北はじめさまざまな地域に出入りするようになって現在に至ります。自分の立ち位置は、当時からずっと考えさせられている事柄のような気がします。そういう人は、庄子さんや私以外にもいるように思います。そういうことをうまく振り返り、知見をまとめるようなことができればいいように思いました。
【土居】
池袋西口をめぐって取り組まれている共同研究の方法論として、考現学に着目されたことに、あらためて関心が惹かれました。かつてないほどに研究倫理が問われる時代に、いかに人間(他者)を眺めることができるかを考えた際、生活学会でこそ考現学的手法をブラッシュアップする議論が可能なのではないか、とも思いました。
また直近に開催された、福島での学術大会のラウンドテーブルセッションのテーマの一つが「災害被災地の復興に生活学は何ができるか?」でしたが、庄子さんならではの当事者性についての議論は、生活学会という場で共有され、議論が深められることを期待しています。