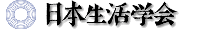2023年10月19日
vol. 21 杉山由里子氏
環境の変化の中で、死と向き合うこと
杉山由里子氏(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 研究員)
インタビュアー:土居浩(ものつくり大学)・大橋香奈(東京経済大学)
*所属などはインタビュー時のものです
日本生活学会研究論文賞の受賞、あらためておめでとうございます。それでは研究フィールドの紹介も兼ねて、これまでの研究歴をお聞かせください。
この春2023年3月のことですが、京都大学の大学院アジア・アフリカ地域研究科に博論を提出して卒業しました。現在はポスドクの研究員として、引き続き所属しています。 私の専門分野としては、地域研究と文化人類学、そして社会学・生活学・死生学にまたがる研究領域になります。大きな研究テーマとしては、「環境の変化の中で、人々は死とどのように向き合っているのか」が関心の中心です。
調査フィールドはアフリカ南部に位置するボツワナで、狩猟採集民として知られる「ブッシュマン」を対象にしています。フィールドでは、彼らが暮らしているすぐ隣にテントを張って、できるだけ長く時間を共有しながら調査をすることを大切にしてきました【写真1】。2015年から現地調査を断続的ですが続けています。「ブッシュマン」の名称は映画タイトルとしても有名ですし、その映画の主人公であるニカウさんは来日したこともあります(もちろん私自身は当時のことを直接に知りませんが)から、アフリカの民族の中では日本で知られている名称だと思います。アフリカでフィールド調査をする以前、学部学生の時は日本で調査をしていたので、いまだに家族(とくに親ですね)には、そんな遠くへ行かないでくれとか、せめてネットが通じるところで調査してくれとか言われてしまいます(苦笑)。そんな風に家族から言われつつも、2015年から累計すると、ボツワナ大学への留学期間もありますから、3年半はボツワナに滞在していると思います。
2023年10月5日
vol. 20 庄形篤氏
運動部活動における体罰を文化人類学的アプローチで考える
庄形篤氏(上智大学 基盤教育センター 身体知領域 講師)
インタビュアー:土居浩(ものつくり大学)・大橋香奈(東京経済大学)
*所属などはインタビュー時のものです
あらためて、日本生活学会研究論文賞の受賞おめでとうございます。まずはご自身の研究フィールドをご紹介ください。
庄形篤(ショウガタ・アツシ)と申します。
専門分野は「スポーツ人類学」でして、日本の運動部活動を対象として、フィールドワーク調査に基づいた研究に取り組んできました。そもそもは、早稲田大学のスポーツ科学研究科で当時教授をされていた寒川恒夫先生(ソウガワ・ツネオ/専門はスポーツ人類学・スポーツ文化論/早稲田大学教授、静岡産業大学教授を歴任)のもとで学んだことに始まります。研究室としては、広義のスポーツを対象として人類学的な研究を行っていました。ここでいう「スポーツ」とは、オリンピックに代表されるような競技スポーツや国際スポーツに限定されるものではなくて、民族スポーツや遊び、舞踊、武術、身体文化などを含めた最広義のスポーツを対象としていました。研究室の先輩方は、特に「民族スポーツ」と呼ばれる特定の民族だけが行うスポーツや伝統武術など、世界中の国や地域のスポーツを研究していました。留学生も多く、帰国子女もおられて、それぞれの関係する国や地域を対象にするなど、各人のアドバンテージを活かしたとでもいうのでしょうか、そのような研究に取り組まれている方々が多かったのです。ただ私にはそのようなアドバンテージが全くないので、研究対象を選ぶ際に迷っていたのですが、寒川先生から、日本の運動部活動も立派な研究対象になり得る、とご助言いただいたことを契機に運動部活動を研究対象にするようになりました。それまで私は、競技者また指導者として運動部活動に関わってきたので、その経験や人脈を活かして調査研究ができるんじゃないのかなと考え、研究対象として選びました。
2021年10月13日
vol.19 吉成哲平氏
「「写真実践」から描き出してゆく、戦後の生活者の営みとその思想」
吉成哲平氏(大阪大学大学院人間科学研究科・博士後期課程)
インタビューアー 土居浩(ものつくり大学)、饗庭伸(東京都立大学)
この原稿はネット・インタビューを行った原稿をインタビューイー、インタビューアーが加筆するというやりとりを経て作成しました
*所属などはインタビュー時のものです
まずはご自身の研究フィールドをご紹介ください。
専門は写真の実践研究、生活環境論、人間と自然の共生です。大阪大学大学院人間科学研究科で三好恵真子先生の環境行動学研究室に所属しています。私の研究室は「実践志向型地域研究」を掲げており、人間の生活の営みを見つめながら、土地々々の望ましい環境の在り方を学際的に討究しています。
もともと高校のときには理系を志望していました。航空宇宙工学の方面に関心があり、いったん某大学の理工学部に進学したものの、一般教養科目で受講した文化人類学に関心が惹かれ、現在の大学へ入り直しました。入学当初は文化人類学や国際関係論の科目等も履修しつつ、授業以外では、たとえば奈良県十津川村で林業に携わってきた方々のライフヒストリーを調べたり、また、三好先生よりご縁を頂き、阪大の学生有志で大阪府能勢町の食育計画に携わったり、学部の様々な取り組みに関わらせて頂きました。
(さらに…)
2021年9月27日
vol. 18 溝尻真也氏
「趣味としての手づくり」の歴史と現在
溝尻真也氏(目白大学メディア学部准教授)
インタビューアー 笠井賢紀(慶應義塾大学)、土居浩(ものつくり大学)、饗庭伸(東京都立大学)
この原稿はネット・インタビューを行った原稿をインタビューイー、インタビューアーが加筆するというやりとりを経て作成しました
*所属などはインタビュー時のものです
日本生活学会研究論文賞の受賞おめでとうございます。まずはご自身の研究フィールドをご紹介ください。
もともとは・・・、いや今でも「メディア研究」が専門です。その中でも音楽を中心に、「音楽メディアのユーザー史」を研究してきました。子どものころからメディアに興味があり、高校生の時には放送部に入って自分で番組をつくったりしていました。それが高じて大学入学後の研究テーマもメディア研究を選び、特に音楽が好きだったので、音楽とメディアについて研究してきました。ラジオやテレビといったメディアは音楽をどう媒介してきたのかが、主な研究テーマです。
修士課程では、特にFM放送の歴史研究に取り組みました。FM放送はAM放送に較べて音質が良かったので、それが音楽ファンの人たちにとってどう重要なメディアになっていくのか、ということを調べました。そして調べていくうちに、オーディオマニアの重要性が見えてきました。初期のFM放送がまだ実験放送の段階で、受信機もほとんど普及していない時期に、その実験放送を誰がどのように聞いていたのかを調べてみたら、自分で受信機を組み立てていたマニアの人たちの存在が浮かび上がりました。その人たちのあいだで「音質のいい、すごいメディアができた」という話が広がっていくところから日本のFM放送の歴史が始まったということが分かり、とても面白いと感じましたね。
こうして、自分の興味の対象が「マニア」に移っていったわけです。自分で受信機を組み立てるような人たちは、何が楽しくてそれをやっているのだろうか、ということを知りたくなり、博士課程ではオーディオマニアへのインタビュー調査に取り組みました。 (さらに…)
2021年9月24日
vol. 17 吉江俊氏
都市論と計画の葛藤を越えて -地方都市のまちづくりと大都市の消費都市論を往還する
吉江俊氏(早稲田大学理工学部講師)
インタビューアー 石川初(慶應義塾大学)、土居浩(ものつくり大学)、饗庭伸(東京都立大学)
この原稿はネット・インタビューを行った原稿をインタビューイー、インタビューアーが加筆するというやりとりを経て作成しました
*所属などはインタビュー時のものです
博士論文賞おめでとうございます。「首都圏の民間による集合住宅供給における住環境価値の商品化と立地地域の変容」という論文ですね。まずはどのようなキャリアを歩んでこられたのか教えてください。
研究者として長いキャリアがあるわけではないのですが、都市計画や都市論を専門にしており、そのうち都市論を大事にしています。
もともと画家を志望していました。理系の受験勉強の合間に絵を描いていたら、やっぱり絵を描きたいなとなり、建築学科に進学することにしました。最初は建築家になりたいと思っていたのですが、大学で出される課題に対して、例えば美術館の設計課題なのに、美術館の展示内容を考えてしまうなど、違うことを始めてしまうような学生で、建物が建つまでの構想が楽しいと思うようになり、早稲田大学の後藤春彦先生の研究室に入りました。
2020年10月31日
vol. 16 武田俊輔氏
長浜曳山祭の都市社会学—フィールドワークから見る地方都市社会と祭礼のダイナミズム
武田俊輔氏(法政大学社会学部教授)
インタビューアー 土居浩(ものつくり大学)、笠井賢紀(慶應義塾大学)、饗庭伸(東京都立大学)
この原稿はネット・インタビューを行った原稿をインタビューイー、インタビューアーが加筆するというやりとりを経て作成しました
*所属などはインタビュー時のものです
武田さんご自身の研究フィールドとキャリアについて、ご紹介ください
専門は社会学です。出身は東京大学大学院人文社会系研究科の社会学研究室で、院生のときは歴史社会学の観点から民謡や民俗芸能を手がかりに、戦前期日本のナショナリズムやメディアについて研究してきました。直接の指導教員ではなかったですが、佐藤健二先生には一番影響を受けています。
2003年に滋賀県立大学に就職してからもしばらくはそういったテーマの研究が中心でしたが、教育面でフィールドワークを重視する学科だったこともあり、それまで、全くやったことがなかったフィールドワークを自分でも実践するようになりました。現在は、地方都市や農山漁村の祭礼や民俗芸能を手がかりとして、地域社会の社会構造や社会的ネットワークを明らかにすることが最も中心的な研究テーマです。 (さらに…)
2020年10月8日
vol. 15 長岡 慶氏
現代ヒマーラヤ世界におけるチベット医学と多重の身体
長岡慶氏(日本学術振興会特別研究員・関西大学)
インタビューアー 笠井賢紀(慶應義塾大学)、土居浩(ものつくり大学)、饗庭伸(東京都立大学)
この原稿はネット・インタビューを行った原稿をインタビューイー、インタビューアーが加筆するというやりとりを経て作成しました
*所属などはインタビュー時のものです
長岡さんご自身の研究フィールドとキャリアをご紹介ください。
専門は医療人類学と南アジア地域研究です。そのなかでも、ヒマーラヤ地域の伝統医療について研究してきました。そもそものはじまりは大学の学部時代で、早稲田大学の教育学部社会科地理歴史専修というところで歴史学や地理学、人類学を勉強していました。一番関心があったのは、「暮らし」のなかの自然と人間の関係です。なので、大学の後半は、自然地理学と文化人類学の二つのゼミで勉強しました。自然地理学のゼミは理系寄りで、地形学や地質学をベースに源流から川を辿って海まで巡検に行ったり、テレビ番組の「ブラタモリ」でやっているような地層の観察といったことをしていました。 (さらに…)
2019年4月12日
vol. 14 浅田静香氏
生ごみを調理用エネルギー源として再資源化 ―ウガンダにおけるバイオマス・ブリケットの生産と生活への浸透
浅田静香氏(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科*)
インタビューアー 真鍋陸太郎(東京大学)、笠井賢紀(龍谷大学)
この原稿はネット・インタビューを行った原稿をインタビューイー、インタビューアーが加筆するというやりとりを経て作成しました
*所属などはインタビュー時のものです
浅田さんご自身の研究フィールドとキャリアをご紹介ください。
私は京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究科(ASAFAS)で博士課程に在籍しています。専門はアフリカ地域研究で、特に東アフリカのウガンダ共和国で料理に使う燃料の研究に取り組んでいます。中心的なトピックとして扱っているのは、バナナの果皮などの生ごみから作られるバイオマス・ブリケット(biomass briquette、以下ブリケット)という固形燃料です。ウガンダでは2000年代から都市の中で、木炭の代替として使用できるブリケットが作られています。そのブリケットがどのように作られ、どうやって人びとの生活に受け入れられているかということが私の大きな研究テーマです。 (さらに…)
2019年1月4日
vol. 13 江口亜維子氏
生活環境にコモンズ的空間を生み出す活動
江口亜維子氏(千葉大学大学院園芸学研究科 博士後期課程*)
インタビューアー 饗庭伸(首都大学東京)、真鍋陸太郎(東京大学)
この原稿はネット・インタビューを行った原稿をインタビューイー、インタビューアーが加筆するというやりとりを経て作成しました
*所属などはインタビュー時のものです
自身の研究フィールドとキャリアをご紹介ください。
現在の研究分野は地域計画学です。千葉大学大学院園芸学研究科で、木下勇教授の地域計画学研究室に所属しています。園芸学研究科ということもあり、造園学ならではのハワードのガーデン・シティ思想を背景とした都市計画思想が根底にあります。その中で、人間の生活を基盤とした空間の計画を組み立てるという教えのもと、私は、場づくりやコモンスペースの研究を進めています。 (さらに…)
2018年9月2日
vol. 12 森下詩子氏
北欧と日本、実践と研究の間から見えてくる “自分ごと” の探究
森下詩子氏(東京大学大学院学際情報学府修士課程/kinologue主宰/クリーニングデイ・ジャパン事務局代表*)
インタビューアー 真鍋陸太郎(東京大学)、笠井賢紀(龍谷大学)、饗庭伸(首都大学東京)
この原稿はネット・インタビューを行った原稿をインタビューイー、インタビューアーが加筆するというやりとりを経て作成しました
*所属などはインタビュー時のものです
まずは森下さんの研究フィールドとキャリアをご紹介ください。
研究といっても、今、修士2年なので研究者と言えるのか?というレベルですが、研究のフィールドはメディア論です。2017年4月から東京大学大学院学際情報学府の水越研究室(メディア論)に所属しています。修士課程は2回目で、以前は社会学で学部のすぐ後に修士へ行きました。
ここ1年やってきて思うのは、1度目の修士課程であった社会学が自分のアカデミックなベースにあるということです。前の大学院を修了してから、ほぼずっと映画配給の仕事をしてきました。2014年からフリーランスでやっています。新卒で映画業界に入った時からのことを考えると、ずっと同じ仕事をしているようで、内容が大きく変化しています。浮き沈みの激しいこの仕事を、20年近く続けていることも奇跡的だと思います。 (さらに…)