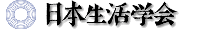『生活学論叢』vol.46 2024
-
論 文
渋谷ハロウィンにおける都市祝祭の現代的特徴
―来街者主体の祝祭としての考察―杉浦 有思
復帰後の沖縄の現実から問い直された「戦後」
―写真家 東松照明が島々で確かめていった生活の実感―吉成 哲平・三好 恵真子
研究ノート
現代中国の民間層の生活世界における武当山武術の展開に関する考察
張 卿・山田 江理男
『生活学論叢』投稿規定・執筆要項
『生活学論叢』vol.45 2024
-
論 文
郷土玩具職人としての模索と矜持
―福島県郡山市デコ屋敷・橋本広司さんの実践から―増藤 雄大
研究ノート
日中「二つの東北」の痛みに向き合いながら生を営むという選択
―「単位制」の弱体化や戦争の痕跡を受け止めつつ災害を乗り越えようとする結婚移住した中国人女性の歴史実践―王 石諾・三好 恵真子
書評
門田岳久著『宮本常一 〈抵抗〉の民俗学―地方からの叛逆―』30
慶應義塾大学出版会、2023年山川 志典
受賞者の声
研究論文賞を受賞して
受賞作『野外飲酒とはいかなる飲み方なのか?
―池袋西口公園における考現学的調査を通して―』関 駿平・庄子 諒・佐藤 裕亮・鍋倉 咲希
『生活学論叢』vol.44 2023
-
論 文
言葉に記憶された舶来品の普及
―「画鋲」「押しピン」「ガバリ」―木村 源知
フィールドワーカーとしての藤森照信
―「いま・ここを歩く」都市経験に向かって―渋谷 慶之
書評
足立己幸編著・衞藤久美著『共食と孤食―50 年の食生態学研究から未来へ―』29
女子栄養大学出版部、2023年宍戸 佳織
『生活学論叢』Vol. 43 2023
-
論 文
野外飲酒とはいかなる飲み方なのか?
―池袋西口公園における考現学的調査を通して―関 駿 平・庄 子 諒・佐 藤 裕 亮・鍋 倉 咲 希
路上販売が紡ぎだすネイバーフッド・エコノミー
―京都市出町エリアにおける焼きいも屋の事例から―有 馬 恵 子
結婚移民として日中「二つの東北」を生きる中国人女性の歴史実践
―ライフストーリーから読み解かれる「満洲」記憶―王 石 諾・三 好 恵真子
「私性」から「公性」へと拓かれてゆく「写真実践」
―復帰前後の沖縄での表現を巡る東松照明の模索―吉 成 哲 平・三 好 恵真子
中山間地域における高齢者の生活行動と最適移動手段に関する研究
―廿日市市浅原地区を事例として―今 川 朱 美
受賞者の声
博士論文賞を受賞して
受賞作『笑いへの離脱/笑いへの拘束
―原発事故後の福島における震災経験とユーモアの生成過程にかんするコミュニケーション社会学的研究―』庄 子 諒
研究論文賞を受賞して
受賞作『セントラル・カラハリ・ブッシュマンにおける社会再編と葬儀
―生と死をめぐる変化への対応―』杉 山 由里子
『生活学論叢』Vol. 42 2022
-
論 文
家庭工作から日曜大工へ
―日本におけるHome Improvementイメージの変遷―溝 尻 真 也
社会転換の荒波を生きる中国農民の「農」をめぐる葛藤と主体的な選択
―施肥に関するライフストーリーから読み解くもう一つの農民像―張 曼 青・三 好 恵真子
研究ノート
襲撃を受けた野宿生活者のスティグマ戦略
白 井 裕 子
第49回研究発表大会 公開公演「生活とアート」(日本生活学会50周年記念事業シリーズ)
大会テーマ「生活とアート」:企画の意図
有 末 賢
基調講演:江戸時代に見る生活の中のアート
田 中 優 子
第1会場 石牟礼道子原作『椿の海の記』の独演への挑戦
井 上 弘 久
石牟礼道子と「言の葉」
古 川 柳 子
第2会場 森下詩子企画 上映とワークショップ ドキュメンタリー映画『〈主婦〉の学校』
大 橋 香 奈・森 下 詩 子
第3会場 武田力ワークショップ 「民俗芸能の復活・創造と参加者の踊り実践」
武 田 俊 輔・武 田 力
『生活学論叢』Vol. 41 2022
-
論 文
「ものがたり」と「ものづくり」からみる都市祭礼の持続
―東京都北区王子における「狐の行列」の事例から―李 婧
基盤型アソシエーションとしての講
―滋賀県栗東市目川の伊勢講勘定帳を読み解く―笠 井 賢 紀
写真家東松照明が直面した「基地の中の沖縄」
―日米の狭間で揺らぐ復帰前の現実と歴史への責任―吉 成 哲 平・三 好 恵真子
受賞者の声
研究論文賞を受賞して
受賞作『運動部活動における体罰肯定と「成長」という認識―事例研究からみる引退後における体罰の再解釈過程―』庄 形 篤
『生活学論叢』Vol. 40 2021
-
論 文
セントラル・カラハリ・ブッシュマンにおける社会再編と葬儀
―生と死をめぐる変化への対応―杉 山 由里子
乾燥地の内陸河川下流において経験された「旱魃」
―イラン・ヴァルザネに暮らす男性たちのライフヒストリーからの考察―西 川 優 花
研究ノート
東日本大震災の仮設住宅地におけるコミュニティの活動性の形成
―大槌町の仮設住宅地の住民運営の実態に基づいて―似 内 遼 一
高齢期における積極的在村離農の可能性 ―元酪農家のライフストーリーを通して―
土 田 拓
公的住宅団地における高学歴技術職の中国籍住民の居住実態と地域との関わりに関する研究 ―首都圏2 団地の住民インタビュー調査から―
王 爽・藤 井 さやか
住宅建材の「銘木」表現にみる素材観の変容 ―戦後昭和期から現在まで―
岡田(泊里)涼子
『生活学論叢』Vol. 39 2021
-
論 文
運動部活動における体罰肯定と「成長」という認識
―事例研究からみる引退後における体罰の再解釈過程―庄 形 篤
「戦争の影」を抱え展開し続ける「写真実践」
―東松照明が生活の現場から証した、長崎の被爆者の生と死―吉 成 哲 平・三 好 恵真子
中国の廃棄物処理施設の建設をめぐる公衆参加の制度化と
手続き的不正義の潜在化
―参加者範囲の縮小による環境リスクの分配的不正義―金 吉 男・小 林 清 治
受賞者の声
今和次郎賞を受賞して
受賞作『世界遺産「白川郷」を生きる―リビングヘリテージと文化の資源化―』才 津 祐美子
博士論文賞を受賞して
受賞作『首都圏の民間による集合住宅供給における住環境価値の商品化と立地地域の変容』吉 江 俊
研究論文賞を受賞して
受賞作『1960‒70年代日本におけるDIY/日曜大工―松下紀久雄と日本日曜大工クラブの軌跡から―』溝 尻 真 也
『生活学論叢』Vol. 38 2020
-
論 文
3世代世帯が多い地域における祖父母の子育て支援に関する研究
―茨城県下妻市を事例として―島 田 由美子・藤 井 さやか
現代社会において有志として地域づくりに取り組む合理性
―新潟県十日町市鉢集落の有志参加型住民組織に着目して―清 水 健 太
ウガンダ農村における婚資が女性の生活にもたらす影響
中 澤 芽 衣
人間の塔チーム「サンツ」における十全的参加者のあり方と位置付け
―潜在的成員に着目して―竹 中 宏 子
石黒宗麿と“京窯”
―京都蛇ヶ谷・八瀬における創作活動と生活―余 語 琢 磨
研究ノート
地形と歴史からひも解く島の漁業とくらしの姿
―瀬戸内海を事例として―関 いずみ・大 西 修 平
ザンビア都市部におけるワイヤーおもちゃの変容
―経済成長とある作り手の製作活動に着目して―川 畑 一 朗
一般女性用防災服開発に向けた災害時の衣料品の準備状況の現状と問題点に関する調査
角 田 千 枝・近 藤 恵
宜興紫砂茶壺の足跡
―近現代陶芸師たちの生活史と創作追求―山 下 由美子
高齢者住宅居住者の居住継続と生活満足感との関連要因
―都心部の公設民営型サービス付き高齢者向け住宅居住者を事例として―馬 場 康 徳